〔 淵野辺から小山田 〕 2017.7.29 町田市 ■ Bootstrap Lightbox [fresh design web] ■ Lightbox for Bootstrap [GitHub] ■ 山&公園へ
【 解説 】
 〔 日枝神社 〕 ( ※ 句読点加筆、算用数字使用 )
〔 日枝神社 〕 ( ※ 句読点加筆、算用数字使用 )
大山咋神(おおやまくいのかみ) 飯綱大神(いいづなのおおかみ) 大鳥連祖神(おおとりむらじのおやがみ)
山王日枝神社は第94代後二条天皇、徳治2年(西暦1307年 今より693年前)大将軍久明親王、執権北條貞時僧となり渕野辺に遊歴して官吏の善悪賞罰を正す。その時各所より溝流れ入り池となり、大蛇あらわれて人民を食せし故、貞時溝内の高山に山王大権現を祈願し、渕野辺伊賀守義博に命じて大蛇をうちころす。住民大いに喜び山王大権現を渕大水有主神として祈願、天文11年8月27日北條氏康関東平定のため、大友義家山王大権現を祈願所とする。其の悪病流行の時、伊賀権現大酉明神のおつげにより知行岡野孫一郎の命を受け、氏子一同8月27日及び11月の酉の日に五穀豊穣氏子安全福作永年を祈る。
日枝神社社殿は天和2年、元禄12年、寛保元年、文化3年等度々の修復をして、現在の社殿は平成25年に再建したものです。
〔 山王日枝神社 〕 この地域の鎮守社で創建は徳治2年(1307年)といわれています。淵辺義博はこの神社で祈願して、この地の住民を困らせていた大蛇を退治したとの話が伝わっています。祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)、大鳥連祖神(おおとりむらじのおやがみ)、飯綱大神(いいづなのおおかみ)。大野北公民館
 〔 やまねの坂( 山王坂 )〕 昔は、やまねの坂と呼ばれていましたが、戦後改修され山王坂とも呼ばれるようになりました。
〔 やまねの坂( 山王坂 )〕 昔は、やまねの坂と呼ばれていましたが、戦後改修され山王坂とも呼ばれるようになりました。
 〔 延命地蔵 〕 本地蔵尊の起縁は鎌倉時代にさかのぼるといわれています。新生児の生命を守るなどの諸願をかなえてくれるとのことで信仰を集めています。
〔 延命地蔵 〕 本地蔵尊の起縁は鎌倉時代にさかのぼるといわれています。新生児の生命を守るなどの諸願をかなえてくれるとのことで信仰を集めています。
大野北公民館
 〔 忠生遺跡B地区(町田市根岸町)〕 この遺跡は忠生区画整理事業に伴い発掘調査された忠生遺跡群(A~D地区)の1つで、境川を見下ろす高台にあり、旧石器時代、縄文時代の集落跡、古墳時代、室町時代の集合墓地跡が発掘されました。中心は縄文時代中期の集落跡で、主に1990~91年に発掘され、竪穴住居跡48軒、堀立柱建物跡4軒、土坑、集石などからなる外径約100mの典型的な環状集落跡であることがわかり、数多くの土器、石器類をはじめ土偶や大珠(だいしゅ)、石棒なども出土しました。同時期の環状集落跡は、川上では相模原市山王平遺跡、川下では忠生遺跡A地区(木曽町)があり、これらの集落とも関係があったと思われます。なお、この説明板後方の下には約4500年前の竪穴住居跡1軒が保存されています。2006年9月 町田市教育委員会
〔 忠生遺跡B地区(町田市根岸町)〕 この遺跡は忠生区画整理事業に伴い発掘調査された忠生遺跡群(A~D地区)の1つで、境川を見下ろす高台にあり、旧石器時代、縄文時代の集落跡、古墳時代、室町時代の集合墓地跡が発掘されました。中心は縄文時代中期の集落跡で、主に1990~91年に発掘され、竪穴住居跡48軒、堀立柱建物跡4軒、土坑、集石などからなる外径約100mの典型的な環状集落跡であることがわかり、数多くの土器、石器類をはじめ土偶や大珠(だいしゅ)、石棒なども出土しました。同時期の環状集落跡は、川上では相模原市山王平遺跡、川下では忠生遺跡A地区(木曽町)があり、これらの集落とも関係があったと思われます。なお、この説明板後方の下には約4500年前の竪穴住居跡1軒が保存されています。2006年9月 町田市教育委員会
 〔 箭幹(やがら)八幡宮随身門(ずいじんもん)〕 町田市指定有形文化財
〔 箭幹(やがら)八幡宮随身門(ずいじんもん)〕 町田市指定有形文化財
特徴 入母屋造銅板葺(いりもやづくりどうばんぶき)、軒唐破風(のきからはふ)付
時期 江戸中期 / 指定年月日 1990年(平成2年)2月14日
随身門とは、神社外郭の門で武官姿の随身像を左右に安置した門をいう。当、箭幹八幡宮の随身門は、桁行(けたゆき)三間(みま)・梁行(はりゆき)二間(ふたま)の入母屋造りの門で、桁行中央の間を通りとして軒に唐破風を設け、両脇間に神像を安置している。軸部は、腰貫(こしぬき)・内法貫(うちのりぬき)・頭貫(かしらぬき)・台輪(だいわ)で固められ桁行の内法(うちのり)は虹梁(こうりょう)を用い、中央は蟇股(かえるまた)で飾られている。柱上は実肘木(さねひじき)付の三斗(みつど)組とし、中備(なかぞなえ)に撥束(ばちつか)を配している。尚、妻飾(つまかざ)り・懸魚(げぎょ)・隅木(すみき)等の一部に後補と思われる改造が見られる。製作年代は絵様(えよう)、刳型(くりかた)及び細部の造りから考え18世紀前半頃と思われる。町田市教育委員会
 〔 箭幹八幡宮由緒 〕 祭神 応神天皇 配祀 神功皇后/例大祭 9月15日
〔 箭幹八幡宮由緒 〕 祭神 応神天皇 配祀 神功皇后/例大祭 9月15日
康平5年 源義家安倍氏を討ち、奥州より帰る途中、木曽に宿り、病にかかって毎夜悪鬼に責められる夢に見た。当社に祈願せしめられたところ、夢に神翁現れ、悪鬼を射倒すと見て病、忽ち快癒した。ここに於いて本宮末社に至るまで尽(ことごと)く再興して神恩に報いたと言い、この時屋根に羽矢を挿入し、又境内に矢竹繁茂せるを以て、箭幹八幡宮と名づけこの地を矢部と称したと伝う。保元平治の乱に敗れた源義賢は大蔵の館に拠り、これを迎撃した源義平は、木曽仲三兼任、渋谷金王丸、鎌田正清等を率いて図師原附近に於いて会戦した。勝敗容易に決せず両軍乱戦死闘、義平の軍危うしと見えた時、突如老翁と童子現れ、矢を拾って郷土軍を援けた。ここに於いて将兵等、これ八幡宮の化身ならんと、神意を恐れ、遂に社前に和睦を誓った。この時甲冑矢の根を埋めた所を根岸と名づけた。後、小山田有重所領17郷の総鎮守として尊信篤く、社地建造物の寄進も多く、社参の道に今も鳥居坂の地名が残っている。寛文5年、代官高木伊勢守大鐘を鋳て鐘楼に掛け、後、代官簗田隠岐守亦社殿を再建して、領民と共に盛大な祭儀を挙行した。明治に至り宮号は廃止されたが、戦後再び古名に復した。祭神の神徳広大、学問、産業、災厄防除の守護神として広く尊信されている。昭和38年4月 奥宮開扉大祭記念 宮司 加藤辰雄 記/井上武 書


 〔 六面地蔵尊 〕 左 :正面から向かって左側のお地蔵さん
〔 六面地蔵尊 〕 左 :正面から向かって左側のお地蔵さん
中央:正面のお地蔵さん。「安永四」の文字が読み取れる。安永4年(1775)と思われる。
右 :正面から向かって右側のお地蔵さん
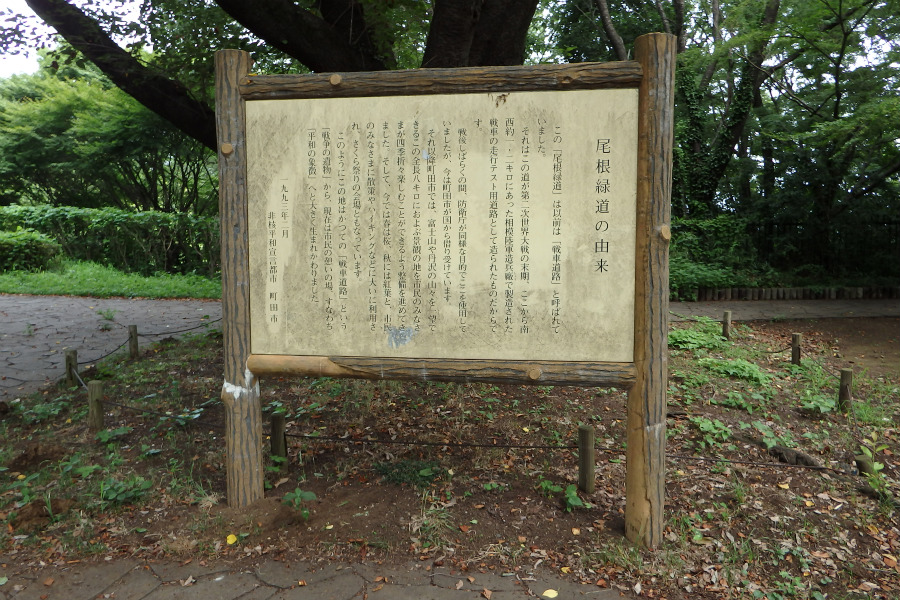 〔 尾根緑道の由来 〕 この「尾根緑道」は以前は「戦車道路」と呼ばれていました。それはこの道が第二次世界大戦の末期、ここから南西約1.2キロにあった相模陸軍造兵廠(しょう)で製造された戦車の走行テスト用道路として造られたものだからです。戦後しばらくの間、防衛庁が同様な目的でここを使用していましたが、今は町田市が国から借り受けています。それ以降町田市では、富士山や丹沢の山々を一望できるこの全長8キロにおよぶ景観の地を市民のみなさまが四季折々楽しむことができるよう整備を進めてきました。そして、今では、春は桜、秋には紅葉と、市民のみなさまに散策やハイキングなどに大いに利用され、さくら祭りの会場ともなっています。このようにこの地はかつての「戦車道路」という「戦争の遺物」から、現在は市民の憩いの場、すなわち「平和の象徴」へと大きく生まれかわりました。1993年2月 非核平和宣言都市 町田市
〔 尾根緑道の由来 〕 この「尾根緑道」は以前は「戦車道路」と呼ばれていました。それはこの道が第二次世界大戦の末期、ここから南西約1.2キロにあった相模陸軍造兵廠(しょう)で製造された戦車の走行テスト用道路として造られたものだからです。戦後しばらくの間、防衛庁が同様な目的でここを使用していましたが、今は町田市が国から借り受けています。それ以降町田市では、富士山や丹沢の山々を一望できるこの全長8キロにおよぶ景観の地を市民のみなさまが四季折々楽しむことができるよう整備を進めてきました。そして、今では、春は桜、秋には紅葉と、市民のみなさまに散策やハイキングなどに大いに利用され、さくら祭りの会場ともなっています。このようにこの地はかつての「戦車道路」という「戦争の遺物」から、現在は市民の憩いの場、すなわち「平和の象徴」へと大きく生まれかわりました。1993年2月 非核平和宣言都市 町田市
 〔 幻の花・カタオカザクラ(片丘桜)〕 この「カタオカザクラ」は、昭和20年5月に長野県塩尻市片丘(かたおか)の山林で発見されたものです。その後、片丘の自生地が山火事に遭い焼失し、幻の桜となりました。東大理学部付属植物園日光分園に移植されていた一本の木から、片丘ザクラ保存会の皆様の永年におよぶ努力により、百数十本がふる里の地に蘇りました。この貴重な「カタオカザクラ」は町田市と桜でつなぐ友好のために、塩尻市より寄贈されたものです。
〔 幻の花・カタオカザクラ(片丘桜)〕 この「カタオカザクラ」は、昭和20年5月に長野県塩尻市片丘(かたおか)の山林で発見されたものです。その後、片丘の自生地が山火事に遭い焼失し、幻の桜となりました。東大理学部付属植物園日光分園に移植されていた一本の木から、片丘ザクラ保存会の皆様の永年におよぶ努力により、百数十本がふる里の地に蘇りました。この貴重な「カタオカザクラ」は町田市と桜でつなぐ友好のために、塩尻市より寄贈されたものです。
平成13年4月7日 町田市
 〔 鶴見川流域 最高度三角点 「山王塚(さんのうづか)」〕 この山王塚跡(あと)には、鶴見川流域最高度三角点「山王塚」(168m)があります。鶴見川は、流域面積235平方kmで、多摩丘陵から下末吉(しもすえよし)台地を刻み、横浜市鶴見区から東京湾に注ぎます。鶴見川の源流は、ここから南に0.6km下った町田市上小山田の「鶴見川源流の泉」です。
〔 鶴見川流域 最高度三角点 「山王塚(さんのうづか)」〕 この山王塚跡(あと)には、鶴見川流域最高度三角点「山王塚」(168m)があります。鶴見川は、流域面積235平方kmで、多摩丘陵から下末吉(しもすえよし)台地を刻み、横浜市鶴見区から東京湾に注ぎます。鶴見川の源流は、ここから南に0.6km下った町田市上小山田の「鶴見川源流の泉」です。
 〔 鎌倉時代の蓮生寺(れんしょうじ)と鎌倉道(かまくらみち) 〕
〔 鎌倉時代の蓮生寺(れんしょうじ)と鎌倉道(かまくらみち) 〕
蓮生寺 この峠から北は現在崖ですが、近年まで鎌倉時代の伝説に関わる古道がこの先北方約900m先の蓮生寺という寺の前へ続いていました。鎌倉時代の公式記録である吾妻鏡(あづまかがみ)の寿永(じゅえい)元年(1182)4月20日条(じょう)には、「源頼朝の父・義朝(よしとも)の」護持僧(ごじそう)であった円浄坊(えんじょうぼう)という僧侶は、頼朝が母の胎内に居る時から祈祷をしていたが、平治の乱以降、京都を出て武蔵国(むさしのくに)に蓮生寺を創建し、頼朝も土地を寄付してこの寺を保護した」とあります。この僧は天台宗比叡山に属したことから、この近くの山王塚(さんのうづか)(多摩市の西の境界点付近にあった)や日枝神社もそのことと無縁ではなさそうです。寺の前からこの峠に続く道には鎌倉道の伝承があり、多摩ニュータウンに伴う発掘調査では鎌倉時代頃の建物跡(あと)や鍛冶場(かじば)跡、土器や陶器、中国製の舶載陶磁器(はくさいとうじき)などが出土しています。また本尊の木像(もくぞう)盧遮那仏(るしゃなぶつ)坐像は円浄坊が京から持参した仏像で藤原様式のものとみられ、また近くの別所長池から出現したという薬師如来像も平安時代末期の地方仏とみられています。
 〔 奥州古道と六部塚(ろくぶづか)~民話の塚と石塔 〕 江戸時代のこと、旅の尼僧が抱く赤子に地元の人が乳を与えましたが礼を言って立ち去った尼僧は力尽きて倒れ峠に葬られました。後日訪れた身内の信州伊那郡(いなぐん)の片桐勘四郎(かたぎりかんしろう)(旅の六十六部)もここで力尽き葬られ、二つの塚を築いた村人は農作業の合間に通っては手を合わせていたそうです。近年この六部塚(六十六部の略)は案内板から南へ80m下った所で見つかり、小山田の田中谷戸集会場では石塔が発見され、民話が本当だったことがわかりました。
〔 奥州古道と六部塚(ろくぶづか)~民話の塚と石塔 〕 江戸時代のこと、旅の尼僧が抱く赤子に地元の人が乳を与えましたが礼を言って立ち去った尼僧は力尽きて倒れ峠に葬られました。後日訪れた身内の信州伊那郡(いなぐん)の片桐勘四郎(かたぎりかんしろう)(旅の六十六部)もここで力尽き葬られ、二つの塚を築いた村人は農作業の合間に通っては手を合わせていたそうです。近年この六部塚(六十六部の略)は案内板から南へ80m下った所で見つかり、小山田の田中谷戸集会場では石塔が発見され、民話が本当だったことがわかりました。
 〔 京と東北を結んだ奥州古道と影取池(かげとりいけ)伝説 〕 多摩よこやまの道に平行して残る山道は、かつて京都と東北地方(奥州)を結んだ奥州古道の痕跡です(奥州古道常盤(ときわ)ルート。国府街道とも)。京都や奈良から関東諸国の国司として赴任してきた有力貴族や郡の警護にあたる衛士(えじ)の往来、また防人(さきもり)の帰郷の道ともなりました。また江戸時代には巡礼の道(武相観音霊場道(ぶそうかんのんれいじょうみち)、東西両国巡礼道)として賑わいました。 * 横面に影取池伝説の案内があります。
〔 京と東北を結んだ奥州古道と影取池(かげとりいけ)伝説 〕 多摩よこやまの道に平行して残る山道は、かつて京都と東北地方(奥州)を結んだ奥州古道の痕跡です(奥州古道常盤(ときわ)ルート。国府街道とも)。京都や奈良から関東諸国の国司として赴任してきた有力貴族や郡の警護にあたる衛士(えじ)の往来、また防人(さきもり)の帰郷の道ともなりました。また江戸時代には巡礼の道(武相観音霊場道(ぶそうかんのんれいじょうみち)、東西両国巡礼道)として賑わいました。 * 横面に影取池伝説の案内があります。
 〔 棚原(たなはら)の館跡(やかたあと)〕 ここから左側(東側)に見える操車場付近にはかつて小高い丘がありました。江戸時代の地誌には戦国時代に八王子城で討ち死にした島崎二郎某(しまざきじろうぼう)の館跡があって鎮守の森や馬場跡もあったと記されています。島崎氏の先祖は鹿島神宮や香取神宮に近い常陸国(ひたちのくに)(茨城県)行方郡(なめかたぐん)の島崎城付近から来たとも伝えられますが詳細は不明です。江戸時代の初め(寛永年間)には加右エ門屋敷(かえもんやしき)もあったと伝えられています。
〔 棚原(たなはら)の館跡(やかたあと)〕 ここから左側(東側)に見える操車場付近にはかつて小高い丘がありました。江戸時代の地誌には戦国時代に八王子城で討ち死にした島崎二郎某(しまざきじろうぼう)の館跡があって鎮守の森や馬場跡もあったと記されています。島崎氏の先祖は鹿島神宮や香取神宮に近い常陸国(ひたちのくに)(茨城県)行方郡(なめかたぐん)の島崎城付近から来たとも伝えられますが詳細は不明です。江戸時代の初め(寛永年間)には加右エ門屋敷(かえもんやしき)もあったと伝えられています。
 〔 日枝神社 〕 ( ※ 句読点加筆、算用数字使用 )
〔 日枝神社 〕 ( ※ 句読点加筆、算用数字使用 )大山咋神(おおやまくいのかみ) 飯綱大神(いいづなのおおかみ) 大鳥連祖神(おおとりむらじのおやがみ)
山王日枝神社は第94代後二条天皇、徳治2年(西暦1307年 今より693年前)大将軍久明親王、執権北條貞時僧となり渕野辺に遊歴して官吏の善悪賞罰を正す。その時各所より溝流れ入り池となり、大蛇あらわれて人民を食せし故、貞時溝内の高山に山王大権現を祈願し、渕野辺伊賀守義博に命じて大蛇をうちころす。住民大いに喜び山王大権現を渕大水有主神として祈願、天文11年8月27日北條氏康関東平定のため、大友義家山王大権現を祈願所とする。其の悪病流行の時、伊賀権現大酉明神のおつげにより知行岡野孫一郎の命を受け、氏子一同8月27日及び11月の酉の日に五穀豊穣氏子安全福作永年を祈る。
日枝神社社殿は天和2年、元禄12年、寛保元年、文化3年等度々の修復をして、現在の社殿は平成25年に再建したものです。
〔 山王日枝神社 〕 この地域の鎮守社で創建は徳治2年(1307年)といわれています。淵辺義博はこの神社で祈願して、この地の住民を困らせていた大蛇を退治したとの話が伝わっています。祭神は大山咋神(おおやまくいのかみ)、大鳥連祖神(おおとりむらじのおやがみ)、飯綱大神(いいづなのおおかみ)。大野北公民館
 〔 やまねの坂( 山王坂 )〕 昔は、やまねの坂と呼ばれていましたが、戦後改修され山王坂とも呼ばれるようになりました。
〔 やまねの坂( 山王坂 )〕 昔は、やまねの坂と呼ばれていましたが、戦後改修され山王坂とも呼ばれるようになりました。 〔 延命地蔵 〕 本地蔵尊の起縁は鎌倉時代にさかのぼるといわれています。新生児の生命を守るなどの諸願をかなえてくれるとのことで信仰を集めています。
〔 延命地蔵 〕 本地蔵尊の起縁は鎌倉時代にさかのぼるといわれています。新生児の生命を守るなどの諸願をかなえてくれるとのことで信仰を集めています。大野北公民館
 〔 忠生遺跡B地区(町田市根岸町)〕 この遺跡は忠生区画整理事業に伴い発掘調査された忠生遺跡群(A~D地区)の1つで、境川を見下ろす高台にあり、旧石器時代、縄文時代の集落跡、古墳時代、室町時代の集合墓地跡が発掘されました。中心は縄文時代中期の集落跡で、主に1990~91年に発掘され、竪穴住居跡48軒、堀立柱建物跡4軒、土坑、集石などからなる外径約100mの典型的な環状集落跡であることがわかり、数多くの土器、石器類をはじめ土偶や大珠(だいしゅ)、石棒なども出土しました。同時期の環状集落跡は、川上では相模原市山王平遺跡、川下では忠生遺跡A地区(木曽町)があり、これらの集落とも関係があったと思われます。なお、この説明板後方の下には約4500年前の竪穴住居跡1軒が保存されています。2006年9月 町田市教育委員会
〔 忠生遺跡B地区(町田市根岸町)〕 この遺跡は忠生区画整理事業に伴い発掘調査された忠生遺跡群(A~D地区)の1つで、境川を見下ろす高台にあり、旧石器時代、縄文時代の集落跡、古墳時代、室町時代の集合墓地跡が発掘されました。中心は縄文時代中期の集落跡で、主に1990~91年に発掘され、竪穴住居跡48軒、堀立柱建物跡4軒、土坑、集石などからなる外径約100mの典型的な環状集落跡であることがわかり、数多くの土器、石器類をはじめ土偶や大珠(だいしゅ)、石棒なども出土しました。同時期の環状集落跡は、川上では相模原市山王平遺跡、川下では忠生遺跡A地区(木曽町)があり、これらの集落とも関係があったと思われます。なお、この説明板後方の下には約4500年前の竪穴住居跡1軒が保存されています。2006年9月 町田市教育委員会 〔 箭幹(やがら)八幡宮随身門(ずいじんもん)〕 町田市指定有形文化財
〔 箭幹(やがら)八幡宮随身門(ずいじんもん)〕 町田市指定有形文化財特徴 入母屋造銅板葺(いりもやづくりどうばんぶき)、軒唐破風(のきからはふ)付
時期 江戸中期 / 指定年月日 1990年(平成2年)2月14日
随身門とは、神社外郭の門で武官姿の随身像を左右に安置した門をいう。当、箭幹八幡宮の随身門は、桁行(けたゆき)三間(みま)・梁行(はりゆき)二間(ふたま)の入母屋造りの門で、桁行中央の間を通りとして軒に唐破風を設け、両脇間に神像を安置している。軸部は、腰貫(こしぬき)・内法貫(うちのりぬき)・頭貫(かしらぬき)・台輪(だいわ)で固められ桁行の内法(うちのり)は虹梁(こうりょう)を用い、中央は蟇股(かえるまた)で飾られている。柱上は実肘木(さねひじき)付の三斗(みつど)組とし、中備(なかぞなえ)に撥束(ばちつか)を配している。尚、妻飾(つまかざ)り・懸魚(げぎょ)・隅木(すみき)等の一部に後補と思われる改造が見られる。製作年代は絵様(えよう)、刳型(くりかた)及び細部の造りから考え18世紀前半頃と思われる。町田市教育委員会
 〔 箭幹八幡宮由緒 〕 祭神 応神天皇 配祀 神功皇后/例大祭 9月15日
〔 箭幹八幡宮由緒 〕 祭神 応神天皇 配祀 神功皇后/例大祭 9月15日康平5年 源義家安倍氏を討ち、奥州より帰る途中、木曽に宿り、病にかかって毎夜悪鬼に責められる夢に見た。当社に祈願せしめられたところ、夢に神翁現れ、悪鬼を射倒すと見て病、忽ち快癒した。ここに於いて本宮末社に至るまで尽(ことごと)く再興して神恩に報いたと言い、この時屋根に羽矢を挿入し、又境内に矢竹繁茂せるを以て、箭幹八幡宮と名づけこの地を矢部と称したと伝う。保元平治の乱に敗れた源義賢は大蔵の館に拠り、これを迎撃した源義平は、木曽仲三兼任、渋谷金王丸、鎌田正清等を率いて図師原附近に於いて会戦した。勝敗容易に決せず両軍乱戦死闘、義平の軍危うしと見えた時、突如老翁と童子現れ、矢を拾って郷土軍を援けた。ここに於いて将兵等、これ八幡宮の化身ならんと、神意を恐れ、遂に社前に和睦を誓った。この時甲冑矢の根を埋めた所を根岸と名づけた。後、小山田有重所領17郷の総鎮守として尊信篤く、社地建造物の寄進も多く、社参の道に今も鳥居坂の地名が残っている。寛文5年、代官高木伊勢守大鐘を鋳て鐘楼に掛け、後、代官簗田隠岐守亦社殿を再建して、領民と共に盛大な祭儀を挙行した。明治に至り宮号は廃止されたが、戦後再び古名に復した。祭神の神徳広大、学問、産業、災厄防除の守護神として広く尊信されている。昭和38年4月 奥宮開扉大祭記念 宮司 加藤辰雄 記/井上武 書


 〔 六面地蔵尊 〕 左 :正面から向かって左側のお地蔵さん
〔 六面地蔵尊 〕 左 :正面から向かって左側のお地蔵さん中央:正面のお地蔵さん。「安永四」の文字が読み取れる。安永4年(1775)と思われる。
右 :正面から向かって右側のお地蔵さん
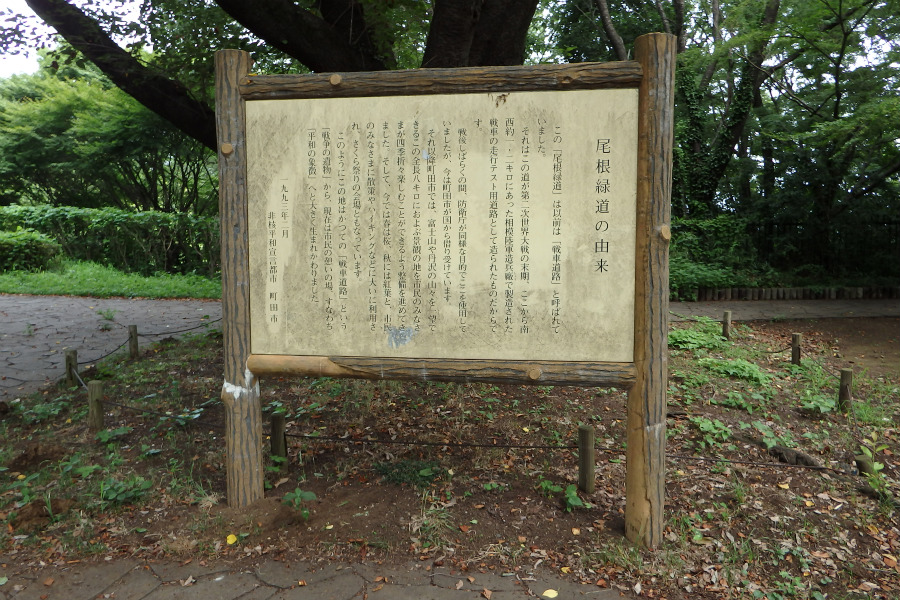 〔 尾根緑道の由来 〕 この「尾根緑道」は以前は「戦車道路」と呼ばれていました。それはこの道が第二次世界大戦の末期、ここから南西約1.2キロにあった相模陸軍造兵廠(しょう)で製造された戦車の走行テスト用道路として造られたものだからです。戦後しばらくの間、防衛庁が同様な目的でここを使用していましたが、今は町田市が国から借り受けています。それ以降町田市では、富士山や丹沢の山々を一望できるこの全長8キロにおよぶ景観の地を市民のみなさまが四季折々楽しむことができるよう整備を進めてきました。そして、今では、春は桜、秋には紅葉と、市民のみなさまに散策やハイキングなどに大いに利用され、さくら祭りの会場ともなっています。このようにこの地はかつての「戦車道路」という「戦争の遺物」から、現在は市民の憩いの場、すなわち「平和の象徴」へと大きく生まれかわりました。1993年2月 非核平和宣言都市 町田市
〔 尾根緑道の由来 〕 この「尾根緑道」は以前は「戦車道路」と呼ばれていました。それはこの道が第二次世界大戦の末期、ここから南西約1.2キロにあった相模陸軍造兵廠(しょう)で製造された戦車の走行テスト用道路として造られたものだからです。戦後しばらくの間、防衛庁が同様な目的でここを使用していましたが、今は町田市が国から借り受けています。それ以降町田市では、富士山や丹沢の山々を一望できるこの全長8キロにおよぶ景観の地を市民のみなさまが四季折々楽しむことができるよう整備を進めてきました。そして、今では、春は桜、秋には紅葉と、市民のみなさまに散策やハイキングなどに大いに利用され、さくら祭りの会場ともなっています。このようにこの地はかつての「戦車道路」という「戦争の遺物」から、現在は市民の憩いの場、すなわち「平和の象徴」へと大きく生まれかわりました。1993年2月 非核平和宣言都市 町田市 〔 幻の花・カタオカザクラ(片丘桜)〕 この「カタオカザクラ」は、昭和20年5月に長野県塩尻市片丘(かたおか)の山林で発見されたものです。その後、片丘の自生地が山火事に遭い焼失し、幻の桜となりました。東大理学部付属植物園日光分園に移植されていた一本の木から、片丘ザクラ保存会の皆様の永年におよぶ努力により、百数十本がふる里の地に蘇りました。この貴重な「カタオカザクラ」は町田市と桜でつなぐ友好のために、塩尻市より寄贈されたものです。
〔 幻の花・カタオカザクラ(片丘桜)〕 この「カタオカザクラ」は、昭和20年5月に長野県塩尻市片丘(かたおか)の山林で発見されたものです。その後、片丘の自生地が山火事に遭い焼失し、幻の桜となりました。東大理学部付属植物園日光分園に移植されていた一本の木から、片丘ザクラ保存会の皆様の永年におよぶ努力により、百数十本がふる里の地に蘇りました。この貴重な「カタオカザクラ」は町田市と桜でつなぐ友好のために、塩尻市より寄贈されたものです。平成13年4月7日 町田市
 〔 鶴見川流域 最高度三角点 「山王塚(さんのうづか)」〕 この山王塚跡(あと)には、鶴見川流域最高度三角点「山王塚」(168m)があります。鶴見川は、流域面積235平方kmで、多摩丘陵から下末吉(しもすえよし)台地を刻み、横浜市鶴見区から東京湾に注ぎます。鶴見川の源流は、ここから南に0.6km下った町田市上小山田の「鶴見川源流の泉」です。
〔 鶴見川流域 最高度三角点 「山王塚(さんのうづか)」〕 この山王塚跡(あと)には、鶴見川流域最高度三角点「山王塚」(168m)があります。鶴見川は、流域面積235平方kmで、多摩丘陵から下末吉(しもすえよし)台地を刻み、横浜市鶴見区から東京湾に注ぎます。鶴見川の源流は、ここから南に0.6km下った町田市上小山田の「鶴見川源流の泉」です。 〔 鎌倉時代の蓮生寺(れんしょうじ)と鎌倉道(かまくらみち) 〕
〔 鎌倉時代の蓮生寺(れんしょうじ)と鎌倉道(かまくらみち) 〕蓮生寺 この峠から北は現在崖ですが、近年まで鎌倉時代の伝説に関わる古道がこの先北方約900m先の蓮生寺という寺の前へ続いていました。鎌倉時代の公式記録である吾妻鏡(あづまかがみ)の寿永(じゅえい)元年(1182)4月20日条(じょう)には、「源頼朝の父・義朝(よしとも)の」護持僧(ごじそう)であった円浄坊(えんじょうぼう)という僧侶は、頼朝が母の胎内に居る時から祈祷をしていたが、平治の乱以降、京都を出て武蔵国(むさしのくに)に蓮生寺を創建し、頼朝も土地を寄付してこの寺を保護した」とあります。この僧は天台宗比叡山に属したことから、この近くの山王塚(さんのうづか)(多摩市の西の境界点付近にあった)や日枝神社もそのことと無縁ではなさそうです。寺の前からこの峠に続く道には鎌倉道の伝承があり、多摩ニュータウンに伴う発掘調査では鎌倉時代頃の建物跡(あと)や鍛冶場(かじば)跡、土器や陶器、中国製の舶載陶磁器(はくさいとうじき)などが出土しています。また本尊の木像(もくぞう)盧遮那仏(るしゃなぶつ)坐像は円浄坊が京から持参した仏像で藤原様式のものとみられ、また近くの別所長池から出現したという薬師如来像も平安時代末期の地方仏とみられています。
 〔 奥州古道と六部塚(ろくぶづか)~民話の塚と石塔 〕 江戸時代のこと、旅の尼僧が抱く赤子に地元の人が乳を与えましたが礼を言って立ち去った尼僧は力尽きて倒れ峠に葬られました。後日訪れた身内の信州伊那郡(いなぐん)の片桐勘四郎(かたぎりかんしろう)(旅の六十六部)もここで力尽き葬られ、二つの塚を築いた村人は農作業の合間に通っては手を合わせていたそうです。近年この六部塚(六十六部の略)は案内板から南へ80m下った所で見つかり、小山田の田中谷戸集会場では石塔が発見され、民話が本当だったことがわかりました。
〔 奥州古道と六部塚(ろくぶづか)~民話の塚と石塔 〕 江戸時代のこと、旅の尼僧が抱く赤子に地元の人が乳を与えましたが礼を言って立ち去った尼僧は力尽きて倒れ峠に葬られました。後日訪れた身内の信州伊那郡(いなぐん)の片桐勘四郎(かたぎりかんしろう)(旅の六十六部)もここで力尽き葬られ、二つの塚を築いた村人は農作業の合間に通っては手を合わせていたそうです。近年この六部塚(六十六部の略)は案内板から南へ80m下った所で見つかり、小山田の田中谷戸集会場では石塔が発見され、民話が本当だったことがわかりました。 〔 京と東北を結んだ奥州古道と影取池(かげとりいけ)伝説 〕 多摩よこやまの道に平行して残る山道は、かつて京都と東北地方(奥州)を結んだ奥州古道の痕跡です(奥州古道常盤(ときわ)ルート。国府街道とも)。京都や奈良から関東諸国の国司として赴任してきた有力貴族や郡の警護にあたる衛士(えじ)の往来、また防人(さきもり)の帰郷の道ともなりました。また江戸時代には巡礼の道(武相観音霊場道(ぶそうかんのんれいじょうみち)、東西両国巡礼道)として賑わいました。 * 横面に影取池伝説の案内があります。
〔 京と東北を結んだ奥州古道と影取池(かげとりいけ)伝説 〕 多摩よこやまの道に平行して残る山道は、かつて京都と東北地方(奥州)を結んだ奥州古道の痕跡です(奥州古道常盤(ときわ)ルート。国府街道とも)。京都や奈良から関東諸国の国司として赴任してきた有力貴族や郡の警護にあたる衛士(えじ)の往来、また防人(さきもり)の帰郷の道ともなりました。また江戸時代には巡礼の道(武相観音霊場道(ぶそうかんのんれいじょうみち)、東西両国巡礼道)として賑わいました。 * 横面に影取池伝説の案内があります。 〔 棚原(たなはら)の館跡(やかたあと)〕 ここから左側(東側)に見える操車場付近にはかつて小高い丘がありました。江戸時代の地誌には戦国時代に八王子城で討ち死にした島崎二郎某(しまざきじろうぼう)の館跡があって鎮守の森や馬場跡もあったと記されています。島崎氏の先祖は鹿島神宮や香取神宮に近い常陸国(ひたちのくに)(茨城県)行方郡(なめかたぐん)の島崎城付近から来たとも伝えられますが詳細は不明です。江戸時代の初め(寛永年間)には加右エ門屋敷(かえもんやしき)もあったと伝えられています。
〔 棚原(たなはら)の館跡(やかたあと)〕 ここから左側(東側)に見える操車場付近にはかつて小高い丘がありました。江戸時代の地誌には戦国時代に八王子城で討ち死にした島崎二郎某(しまざきじろうぼう)の館跡があって鎮守の森や馬場跡もあったと記されています。島崎氏の先祖は鹿島神宮や香取神宮に近い常陸国(ひたちのくに)(茨城県)行方郡(なめかたぐん)の島崎城付近から来たとも伝えられますが詳細は不明です。江戸時代の初め(寛永年間)には加右エ門屋敷(かえもんやしき)もあったと伝えられています。















































































